
| 教会の紹介 | 集会案内 | 牧師室より | 健 康 | 原宿ニュース | お葬式 | 英語学校 | |
| TIC | 公文教室 | 関連リンク | クリスマス | TOP |
| バックナンバー |

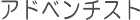
|

|
2006年8月 第237号 
「八月のレクイエム」 熊谷 幸子 亡き人を偲び、はるかな日々を手繰る八月。終戦記念日と旧盆のある日本の八月は、死者と生者を交差させる。 「死者の記憶が遠ざかるとき、同じ速度で死は私たちに近づく」と、詩人の故石垣りんさんは「弔辞」と題した詩の中に書いた。 弔という字は、とふらう・いたむ・あわれむ・終りを問うの意味を持つ(白川静『字統』より)。古くは、屍を野に置き、風化を待って骨を納めたが、鳥獣を追い払うため屍のまわりに立つ人は弓を携えた。現代の告別式に私たちは弓矢を持だない。けれど死が大切な人を奪っていくことに変わりはない。遠された者は張りつめた心に、弦に代わって言葉を張る。そうして死を受け容れ、生を見つめ直し、その意味を自らに問うのである。 信徒となって、五人の方々に私も弔辞をお捧げした。一年前の八月には、鴨田増一先生に捧げた。それでもまだ先生がこの世のどこかに生きていらっしゃるように思われてならない。死を認めることは本当に辛く受け入れ難いことなのである。 葉月八月は、また、旅する月。陸と空を大勢の人々が移動する。短い生涯を旅に明け暮れたモーツァルトの今年は生誕250年である。 11歳で「葬送カンタータ」を作曲し、22歳で最愛の母を失ったモーツァルトの生の下には、常に死が重層をなして流れていた。けれど31歳で旅先から父にあてた手紙の中には、 “死は…心を安らかにし、慰めてくれるものとなったのです! 神様は私に機会を与えて、死が私たちの幸福にいたる鍵であることを知る幸いをお恵み下さいました。”(カール・バルト 『モーツァルト』〔小塩節訳・新教出版社刊〕より)と、書き遺している。 そうであればこそモーツァルトは、絶え難い悲しみを超えて平安に達し、清らかに朗らかに神の創造の世界を称え上げられたのだ。 その八月に、モーツァルトの最後の作品「レクイエム」を聖歌隊が歌い、オーケストラが奏で、初めての追悼会を教会で行うことができるのは、神様の大いなるみ恵みである。 1950年代から今年に至る139名の眠りにつかれた教会員のリストをつくりながら、私は、そのお一人お一人の生涯には、かけがえのない命の物語があったことを想い、胸を突かれた。そして同時に、ご再臨の約束がいかに大きな慰めであり希望であるかを改めて確信した。私たちに再会はあっても、永遠の別れはない。 遠い記憶を辿りながら、新しい記憶をつくる八月。その追悼の午後、立ち去った人々を共に偲び、レクイエムの調べに、信仰の先達と懐かしく愛しい人の遺した言葉に耳を傾けてみよう。目をはるかな見えないものに向けてみよう。今ここに生かされ、教会に繋がっているのは、共に偲ぶ命があったからこそ。この深く瞑想する月に、この聖句の深さを想う。 “彼は死んだが、信仰によって今もなお語っている”(ヘブル11 : 14) (東京中央教会長老) |

